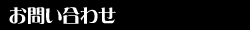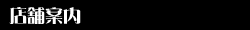「ハックニー・ダイアモンズ」の流れから続くローリング・ストーンズ祭り。
今回のYouTubeでは「ストーンズを感じる10枚」としましたが、ストーンズ本体のレコードをデビューから順にレビューしたことを思い出しまして、探してみたら、それが見つかりました。
8年前に書いたものなので、だいぶ自分の中でも評価が変化していますし、知識も文章も拙いですが、これをまとめてみたいと思っていましたので、今回のこのストーンズ祭りをきっかけに、一挙に紹介したいと思います。
一枚のアルバムから好きな曲をYouTubeの動画で紹介していくスタイルで書いておりますので、ちょっと文章だけにするとおかしい部分があります。
何卒、ご了承ください。
「デッカ/ロンドン」時代はUS盤での紹介です。
当店では福岡のローリング・ストーンズのレコードやロックのレコードを買取しております。
England’s Newest Hit Makers
気になったのがこの曲。
「You Can Make It If You Try」。
ちょっとジェイムス・ブラウンの「プリーズ、プリーズ、プリーズ」にたゴスペル調の曲。
意外にガール・グループにもある曲調だったので、気になって誰のカバーか調べると、オリジナルはジーン・アリスン。
アリスンはゴスペル・グループの名門フェアフィールド・フォーにも少し参加後、スカイラークスなどを経て、ソロとして活躍。
当時のUKグループとはやはり違う渋く黒っぽいカバーです。
このファースト、フィル・スペクターが参加しているが、特にスペクター的な音は感じない。
R&Bを得意とする実力派ロック・グループ。
半端なくマニアックな趣味なのに、成長しつつ転げて行く伝説のロック・グループのファーストにふさわしい。
十分これ一枚で歴史に残る。
逆に後が凄過ぎたので、あまり聞かれないのは皮肉なものである。
12×5
チェス録音を含む12曲。
一曲目の「Around And Around」を推す。
チャック・ベリーのカバーだが、ギターの音、二本の絡み、リズムの取り方が、後のストーンズ・スタイルを感じさせる。
もう一曲印象に残ったのがフォーク・ブルース調の「Good Times, Bad Times」。
この手のバラードも後々得意となっていくだけあって、段々とローリング・ストーンズならではのスタイルが出来上がっている。
ブルースの本場チェスに乗り込むだけあり、妥協は一切無い黒さを感じさせる。
アシッド・ジャズふうにスイングするインスト・ナンバー「2120 South Michigan Avenue」はハモンド・オルガンが効果的。
クラブDJ受けそうでグルーヴィー。
「Around And Around」はライヴ映像(口パク?「タミー・ショー」)があったけど、ミックのダンスがジェイムス・ブラウンしていて若い(同日、本家JBも出演した。有名なパフォーマンスのひとつ)。
「Congratulations」。
カントリー調であり、メンバーのコーラスも後のストーンズふうだ。
この時代には、ちょっと一風変わった、黒っぽさを感じさせない曲。
カントリーやサザン・ソウルに食い込み、ブルースだけでないアメリカ南部に寄った「ベガーズ・バンケット」の影がチラホラ聞こえる。
曲はジャガー=リチャーズのオリジナル。
ちなみに次の「Grown Up Wrong」は出だしはブルース・ギターだが、音にサイケの色も感じさせ、リズムはスイングしている「プレ・サタニック・マジェスティーズ」というか、ガレージ・サイケ色がする。
これもジャガー=リチャーズ。
オリジナルにも段々と磨きがかかってきている。
The Rolling Stones, Now!
「Down Home Girl」。
段々とミックの歌い方が今に近い独自のものとなってきており、演奏に余裕が出来つつある。
この曲はジェリー・リーバーとマイク・ストーラー作曲、オリジナルはアルヴィン・ロビンソン。
ニューオリンズやルイジアナの香りがするファンキーな一曲。
ボ・ディドリーのジャングル・ビートのようなリズムは過去にもあったが、ストレートなブルース、R&Bカバーに終始していたころより、トコトコと奏でるチャーリーのドラムスやワイマンのベース、声を張り上げる時のミックのシャウトやトーキング的な部分は、今現在のストーンズ・スタイルに近い。
アルヴィン・ロビンソンのヴァージョン聞いたが、凄まじくヘヴィな歌い手。
野太い声で歌われるニューオリンズR&B。
ホーン・セクションの切れも凄まじく、ついでに紹介しておく。
CD化されていないのは残念。
ダウン・ロードで4曲程あった。
リーバー=ストーラーの「レッド・バード」で活躍してるだけあって、彼らのお抱えグループ、コースターズ・ヴァージョンも素晴らしいので紹介する。
Out Of Our Heads
もうストーンズ・スタイルが完成させれている。
ドン・コヴェイのカバーである一曲目の「マーシー・マーシー」。
出だしのギターに尽きる。
オリジナルのコヴェイのギターにはないワイルドさがストーンズらしい。
その後もディストーションの効いたギターがバックで唸る。
2曲目のマーヴィン・ゲイのカバー「ヒッチ・ハイク」もシンプルな曲調ながら、ギター・ソロを入れたりと、飽きさせないグルーヴを作り上げている。
単なる黒人カバーからロックへと飛躍したエポック・メイキングなアルバム。
そして決定的な代表曲「サディスファクション」。
野太いキースのギター・リフにミックの怪しげな歌唱の対比。
ブリッジ部分の格好良さ。
2010年代に入っても、スタジアムでやっても色あせない。
こう書いていくとストーンズのギター・スタイルが完成されたアルバムだとも言える。
今の所、私個人の初期名盤。
後半がちょっと弱いが。
Big Hits: High Tide And Green Grass
続いてアメリカで発売されたのは初のベスト盤です。
カバーの多い、黒っぽさはで埋め尽くされた過去の渋いアルバムとは違い、シングルで発売されたポップな曲が多いため、過去のUSオリジナル・アルバムとは雰囲気が違う。
さらに個人的にストーンズ初体験時(初来日頃)に聞いたアルバムでもあり、その頃はゼムやアニマルズの黒いロックで粋がっていて、ポップな曲調が多いこのアルバムは18歳当時の私には分からなかった。
しかしながら、今聞くと、ジャック・ニッチェならではのハリウッド録音を中心に、ミックのポップ・スターとしての魅力が存分に発揮されたアルバムだと言える。
よって「ローリング・ストーンズ=不良のロック」のイメージで、最初に聞いて挫折した過去も、さもありなん。
象徴的なのがこの「As Tears Go By」。
このストリングスのアレンジはジャック・ニッチェかと思ったら違う。
マイク・リーンダー。
なんとビートルズの「シーズ・リーヴィング・ホーム」のあの美しいストリングスも手掛けていた人だ。
甘酸っぱいローリング・ストーンズが詰まった濃い青春ポップス時代は、強烈なキースのギター・リフとミックの妖しさが炸裂するロック、一曲目の「サディスファクション」で完結する。
Aftermath
全てジャガー=リチャーズ曲で製作された初のアルバム「アフターマス」です。
そんなに最初は好きではなかったのですが、聞いていくうちに味わい深くなってきました。
好きな曲は3つ。
まずはこのバラード「Lady Jane」。
弦楽器三本(キース、ブライアン、ワイマン)が絡む様が美しい。
特に後半部分の間奏のアンサンブル。
ブライアン・ジョーンズが弾いてるのがタルシマー。
「Paint It, Black」でのシタールなど、ブライアンの「ワールド・ミュージック」的要素がバンド内に浸透し、ミック、キース、ブライアンの3人のバランスが取れたより幅広い音楽性がこのアルバムから垣間見れる。
「Doncha Bother Me」はブルースのカバーかと思ったら、彼らのオリジナル。
カバーではないストーンズ・オリジナル・ブルース。
そして最後の「Going Home」では、ブルース・ジャム風の10分を超える大作で、ミックのオーティス・レディングふうソウル歌唱で、どんどん盛り上げていく。
ブライアンのエキゾチック風味、ミックののたうち回るシャウト、ブルースの呪縛的な妖しさ、未完成ですが、彼らのルーツが詰まった第一歩の始まりです。
Got Live If You Want It
初のライヴから「I’ve Been Loving You Too Long」オーティス・レディングのカバーです。
ガレージ・ロックのような勢いのあるライヴの中で、ミックがじっくり歌うバラードです。
何とも青臭いのだが、一生懸命歌う姿に、女性ファンが熱狂します。
昨年出版されたクリストファー・アンダーセン著「ミック・ジャガー~ワイルド・ライフ~」。
図書館で少し読んだのですが、とても面白い。
ミックのセクシャルな魅力が最大限に描かれていて、作者の文章もうまい。
これとキース・リチャーズの自伝「ライフ」も面白いらしい。
個人的にはミュージシャンの人なりには興味がないのだが、ローリング・ストーンズに関してだけは、「人なり」から「音楽性」まで、全てが魅力的。
ミーハーからマニアまで熱狂させる。
ミックのオーティス・カバーは、これを象徴しています。
追伸:この曲は疑似ライヴだそうです…。
Between the Buttons
さてUS盤ではお馴染みの曲がいっぱいのアルバムです。
世は1967年「スウィンギン・ロンドン」の時代。
シェイクするリズムや、スイングするサンド満載。
1990年代のころ、クラブ・ブームの頃やモッズ好きには一番好評だったのでは。
個人的にその手よりブルースやR&B好きな私は、よく出来たアルバムだとは思う反面、物足りない。
コクのあるブルース・フィーリーングやロックンロールはどこに?
キース(ブライアン?)のチャック・ベリーふうギターが炸裂する「Miss Amanda Jones」は、スイングする縦のビートより、ストーンズらしい。
しゃがれ声で歌うミックもセクシー。
ちょっとラップに似たアジテーションのような得意の叫びも聞ける。
最後の男性コーラスもキマってる。
これらも含め地味めなB面の方が好み。
Flowers
「う〜ん」と考えてしまう。
A面はベスト的選曲。
B面はフォーク・ロック調、サイケ調、ソフト・ロック…時代と共にブルースから離れて行く。
既出だがこれぞローリング・ストーンズ的な「Let’s Spend The Night Together」にしようかと思ったが、あえて「Flowers」なりの選曲をと考えた末…。
「Please Go Home」はボ・ディトリーふうのジャングル・ビートに、この楽器はなんだ?サイケ風味をまぶしたストーンズ流サイケ。
ストレートなミックの弾語りフォーク調の「Back Street Girl」も良い。
「Ride On, Baby」で使われるコミカルな楽器類。
これはブライアン・ジョーンズのアイデアか。
高揚していく曲調に、サビの部分のハープシコードの高音にカタルシス。
途中のマリンバといい、この面白くて楽しい曲に一票。
段々とこのアルバム好きになってきた。
そしてこのアルバムがブライアン・ジョーンズによるところ大きく、ブライアンのセンスに感嘆する。
Their Satanic Majesties Request
続いては問題作「サタニック・マジェスティーズ」。
注目すべきは「Gomper」のモロッコ音楽らしきリズム。
あるいは細かなリズムを刻むわけではないが、ジャマイカの「ナイアビンギ」にも似た雰囲気もある。
あるいはジャズの「アート・アンサンブル・オブ・シカゴ」なんて思い出した。
ジョージ・ハリスンがインド音楽に傾倒していたビートルズに対し、ブライアン・ジョーンズは中近東、地中海音楽などを取り入れ、十分に「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」に対抗しうるアルバム体制は整っていたのだが、他のメンバーとブライアンの関係が最悪だったのか、コンセプト・アルバムにしては雑然としていて着地点がない。
その猥雑さがストーンズらしいと言えばらしいが…。
この「Gomper」から「2000 Light Years From Home」へ移るタイミングでの、ゴダール映画の場面展開のようなSEふうの音がかっこよく、「2000 Light Years From Home」のムーグのSF音楽的なサウンドも独特、次のボーカルを電気処理したかのようなミックの語りのような声も宇宙人みたいで、アルバム全体を通して、このような呪縛的で前衛ポップアートのような音楽を作り上げていたら、大傑作として世に残っていたはず。
AppleのiMacのCMにも使われた「She’s A Rainbow」といい、モンド・スペースエイジ・ミュージックとして、B面は傑作だと思う。
この曲が好きな人やブライアンのソロが好きな人には、北アフリカ音楽「グナワ」を集めたオムニバス「マラケシュでお茶を」をお勧めする。
私が21世紀、一番衝撃を受けたアルバムだ。
Beggars Banquet
ここからは完全にアメリカ南部を主体にミックとキースが主導権を握る。
ストーンズ黄金伝説はここから始まります。
ダウン・トゥ・アースなサザン・ソウルふうの気怠くもグルーヴするリズム、全編をさまようキースのギター、ミックの抑制と躍動感が入り交じるボーカル、全てが一体となることで、バンドの勢いも加速していきます。
しかしながら一曲目の「Sympathy For The Devil」は前作「Their Satanic Majesties」のB面から続く延長上にあることを実感。
ブライアンは殆ど参加していないが、ストーンズはアフリカ音楽をはじめ、色々な国の音楽を取り込んでいき、比類無き巨大ロック・バンドに成長したのだ。
「Their Satanic Majesties Request」はけっして失敗作ではなかった。
棄て曲がないので、どれを紹介していいのか分からないが(殆ど耳タコ状態というのもある)あえて、この小品「Prodigal Son」。
戦前ブルースマン、ロバート・ウィルキンスをさりげなくカバーし、アルバムをクールダウンさせる業。
実に「鯔背(イナセ)」です。
Through The Past, Darkly (Big Hits Vol. 2)
続いてはベスト。
ライヴ定番多し一枚。
「Honky Tonk Women」。
チャーリー・ワッツのドラムが南部フィーリングを醸し出しています。
その後「Sticky Fingers」では本格的にマッスルショールズで録音します。
ブライアン亡き後のシングル第一弾。
ミックとキースのアメリカ音楽ルーツ偏向が功を奏した一曲。
アシッドなロンドン・サイケ色をバンドに持ち込んでいた
ブライアンの死が(実際亡くなったのは脱退後だが)成功をもたらすとは皮肉なものです…。
Let It Bleed
英デッカ最後のスタジオ・アルバムは名盤中の名盤、
ロック史上最高のアルバムの一つである「Let It Bleed」。
全くもって独自のストーンズ・グルーヴを作り出しており、付け入る隙もなし。
このアルバムにレビューを書くなんてもってのほかであるが、あえて一曲選ぶとすると、キース・リチャーズのギターが大活躍して、イアン・スチュワートのピアノがグルーヴを作り上げるタイトル曲。
キース大活躍と書いたが、曰くこのアルバムはキースに寄る所が大きいとか。
このアルバムをまとめたジミー・ミラーのプロデュース能力も買うべきか。
トラフィックを改めて聞きたくなった。
プライマル・スクリームも「スクリーマデリカ」はミラーによるもの。
どちからというとプライマルは「ギヴ・アウト・バット・ドント・ギヴ・アップ」の方がストーンス色が強い気がするが、こちらも改めて聞いてみよう。
ちなみに「ギヴ・アウト〜」のプロデュースはトム・ダウド。
確かにミラーよりダウドの方がアメリカ南部の色が強い。
ブライアンへキースが一矢を報いアルバムとも言える。
その辺の真相をキースの自伝「ライフ」から知りたい。
なかなか購入して読む暇がない。
Get Yer Ya-Ya’s Out!
次はライヴです。
「Jumpin’ Jack Flash」の印象は「ブギー」「ブギウギ」。
ギター、ベース、ドラムの小編成ロック・コンポなのに分厚い音。
まさにエレクトリック革命。
もちろん当時クリーム、レッド・ツェッペリン、ジミ・ヘンドリックス等もいたが、メンバー全員の一体感から生み出される力強さは、これまでの歴史の長さと、今も生き続ける現役バンドであることが物語っている。
この曲と最後の「Street Fighting Man」が特に良い。
チャック・ベリーの「Carol」でさえ図太い音に変身。
チャーリー・ワッツが飛び跳ねるジャケは軽快なイメージを想像させるが、裏腹に重厚なロック・アルバムだ。
The Rolling Stones Rock and Roll Circus
続いては1990年代に入り発売された
1968年12月のTVショウ「ロックンロール・サーカス」から。
ジョン・レノンの声は圧倒的だし、オノ・ヨーコのスクリーミングもサーカスに華を添える。
ザ・フーの演奏を聞いてこの映像をお蔵入りさせたのも頷ける。
タジ・マハールのR&Bなロックンロールも力強い。
肝心のストーンズですが確かに印象に残る演奏でもない。
あえて選ぶとしたら「Sympathy For The Devil」でしょうか。
1968年当時のサイケ、ヒッピー文化を象徴するショウでの大団円てなことで。ミックの悪魔的なパフォーマンスは圧巻です。
これは映像で観るべきものだと実感(映像はCDを聞いた後に観た)。
Sticky Fingers
このアルバムのレビューはなかなか苦戦しています。
とても美しい流れで、どれこれも完璧すぎて…。
ロック・アルバムの象徴とも言うべきアルバムです。
「Brown Sugar」のリフもかっこいいですが、好みはバラードの「Wild Horses」。
これがいかにもマッスルショールズの音です。
この地のソウル・バラードの類いで言えば、パーシー・スレッジの「男が女を愛するとき」。
これのストーンズ版とも言うべきか、ベタだけど良い。
ブライアン・ジョーンズが去り、統一感のある音作りに。
ミック・ジャガーがこのアルバムを愛する理由も分かる。
「Sticky Fingers」が彼らにとって最大の成功傑作だったと思うけど、
あのストーンズにあった「如何わしさ」が、アルバム全体に色濃く出たサザン・ソウルの美しいサウンンドにあったかどうだか分からない。
よく出来たアルバムには違いない。
Exile on Main St.
このアルバムは方向性を再びブルースやロックンロールの戻した上で、二枚組の濃いアルバムに仕上げた結果、ストーンズらしい「如何わしさ」を取り戻し、デッカ時代のサウンドとローリング・ストーンズ・レコードの洗練さが一つになって、大傑作と成り得たのだ。
「Rip This Joint」、
ストレートなロックンロールなこの曲でのボビー・キーズのサックスはオールド・ロックンロールやR&Bのようにご機嫌極まりなく、よくぞここまでオールドなものを現代音楽の最先端(1972年当時)に仕上げたものだ。
ルーツ音楽を源にした強さ、およそ60年ロックンロールが生まれた頃から始まるバンドでありながら、常に最先端に身を投じるミック・ジャガー。
生きる伝説である理由がここにある。
そのこと自体を存分にアピールしたアルバムからの一曲のひとつ。
もちろんこのアルバムがこれ一曲で象徴できるわけがないが。
Goats Head Soup
1973年発売「山羊の頭のスープ」。
熱きロックの時代は終わり、グラム・ロックやシンガーソングライターなど、ストーンズの音が時代遅れになりかけたのか、目新しさは感じられず現状維持だが、一定のレベルの佳作には仕上がっている。
「Dancing With Mr. D.」「100 Years Ago」「Star Star」「Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)」
これらのファンキーでポップな曲調は、来るべき名盤「Black And Blue」や「Some Girls」への序章。
取り上げたのは「100 Years Ago」。
ミック・テイラーのむせび泣くギターと、ビリー・プレストンのクラビネットが活躍する。
ミックよりキースより他のメンバーが目立つところが、このアルバムに物足りなさを感じてしまう所以か。
It’s Only Rock ‘N Rol
これまた佳曲揃いの作品だが、「たかがロックン・ロール」。
タイトル名の開き直りに当時のストーズの苦戦と停滞が象徴してる感がする。
どうも煮えきれないアルバム…。
もちろん演奏は素晴らしい。
「Till The Next Goodbye」でのチャーリー・ワッツのドラムは、サザン・フィーリングを醸し出した最高の出来だし、キャッチーなリフがかっこいいタイトル曲と「If You Can’t Rock Me」、
ミック・テイラーの流暢なギターが聞ける「Time Waits For No One」など、魅力を語るときりがない。
なのだが、ガツンと来ない。
最初一曲選ぶとしたら「Black And Blue」へと繋がるファンキーな「Fingerprint File」と思ったが、先ほどのチャーリーのドラミングが素晴らしい「Till The Next Goodbye」が渋いのでこちらを選ぶことにした。
Black And Blue
前2作での「曲は良いがインパクトに欠ける」。
これはシンガーソングライター等のアルバムなら十分なのだが、インパクトを与え続けたストーンズには物足りない。
個人的な趣味もありますが、ミック・テイラーの美しいギターより、酔いどれロン・ウッドへのメンバー・チェンジはストーンズに新しい刺激を与えたのでは。
「Black And Blue」は、ロック・バンドがファンクやレゲエを飲み込み、モンスター・バンドの金字塔を打ち建てた。
ちと大袈裟か。
「Cherry Oh Baby」は当時のどのレゲエよりも鯔背で(当時キースがハマったナイヤビンギに近い)「Hot Stuff」は個人的ストーンズの最高傑作。
クールで隙間のある音作りに、緻密なアレンジによる洗練されたファンク・サウンドは唯一無二。
メロディー重視よりリズム重視のアルバムは、肉体的で、新しい世界を見つけたかのように音が弾けて瑞々しい。
変革する大ベテラン。
「転がり続ける石」。
バンド名に偽りなし。
かっこいい。
青を背景にメンバーの顔がドアップになったジャケも最高。
以上、当時の私は力尽きたようで、次の「女たち」以降もいずれ挑戦する気でいます。
ロック、ソウル、ブルース、R&B、日本の音楽、ジャズなどのレコード、CD、買取、出張買取、店頭(持ち込み買取)、宅配買取致します。
福岡市の中古レコード屋・中古CD屋アッサンブラージュ。
◾️アッサンブラージュ公式X(旧:Twitter)
◾️アッサンブラージュ公式Xインスタグラム
◾️アッサンブラージュ公式YouTube